| 第3回 基礎の混色 Vol.1 2002/
10/ 17/ Thu. |
|
|
今回は混色の基礎知識です。
上絵具は焼成前と焼成後での色彩の変化が少ないということを前回お話しましたが、制作の折には2色以上の色を混ぜて描画することが多いので混色の基本は知っておきたいものです。 |
混色のコツ
混色は「覚える」というよりも「慣れる」というような感覚的なものですが、まずは右図にある12色相環に出てくる色の中から2色をランダムに選び、それを1:1で混色した場合どのような色になるかを、おおよそにイメージ出来るようになることです。
|
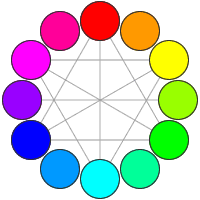 |
混色の実際
| 例 - 1 |
| ① |
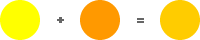 |
| ② |
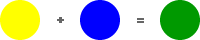 |
これはやさしいですね。
それではこれはいかがでしょうか? |
| 例 - 2 |
| ① |
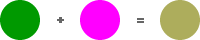 |
| ② |
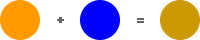 |
例 - 1 の①のように色相環で近い位置にある混色は比較的イメージしやすく、例 - 1の②のように色相環では離れていても絵を少しかじった事がある人にはイメージしやすい色もあります。
しかし、例 - 2の混色のようになると、なかなかイメージしにくくなります。まずは基本の12色の混色をしっかりとイメージ出来るようになることからはじめましょう。
| 注意点 |
| 絵具の混色の場合は、顔料の着色力や透明・不透明によって上記の例から、ずれることもあります。また上絵付けの場合、混色制限も当然生じてきます。この点については、やはり経験が必要となってくるのが難しい所です。また12色相環には出てきませんが、無彩色(黒やグレー)が混色で果たす役割も押さえておかなければなりません。また、むやみに混色数を増やすと鮮やかさ(彩度)が低下して鈍い印象の発色になる点も気を付けなければなりません。
|
|
|
| 上絵付けで覚えておくと便利な混色 |
| ① |
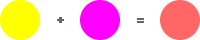 |
果物のシェード、肌の赤味、黄色の花のシェードなど |
| イエロー ピンク系
|
| ② |
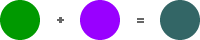 |
葉の弱いシェード、やや遠目の樹木など |
| 明るい緑 ライラック系 |
3色以上の混色や混色制限、無彩色を加えた混色については別の機会にお話したいと思います。 |
|
|
|
|
|